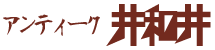京都では、毎月行事やイベントがあちこちで催されています。
どの季節も楽しい京都。浴衣で行きたい行事やイベント、おすすめのお花見スポット等をご紹介!
※コロナウィルス禍の状況等により変更・中止となる場合がございます。訪れる際は必ず確認下さるようお願いいたします。
京の花たより
紫陽花


三室戸寺 ~7/11まで
京都で紫陽花と言えば、必ず名前の挙がる明星山三室戸寺。
2万株の様々な紫陽花が堪能できます。
紫陽花に囲まれての撮影スポットも多数ありますよ!
紫陽花の恋お守りは記念にピッタリです。
桔梗


東福寺・天徳院 ~7/18(特別公開)
受付10:00~17:00 ライトアップ受付18:00~20:00
数少ない桔梗の名所です。
普段は入れないお寺に、桔梗の季節だけ特別に拝観させて頂けます。
アットホームな雰囲気のお寺でしたので、のんびりとくつろげました。
ゆっくりとした時間をお過ごしください。
廬山寺 6月下旬~9月上旬(例年の見頃)
何と1千株の桔梗が‼
紫式部の邸宅跡と言われており、「源氏の庭」が有名です。
白い砂と、緑の苔、紫の桔梗のコントラストが素敵です。
半夏生


※半夏生は「半化粧」とも言われます。開花の頃周りの葉が白色に変化し、水芭蕉の花が咲いたようになります。
そして開花が終わると、また緑色に戻ります。
建仁寺 両足院 ~7/11(特別公開)

普段は非公開の両足院。半夏生の開花時特別に公開しています。
半夏生を見れる場所は中々ありませんので、この機会に是非訪れたいです。
蓮
天龍寺 6月初め~8月上旬
放生池では蓮の花が咲き誇ります。
総門を入ってすぐの所に放生池があります(無料エリア)ので、嵐山に行った際に気軽に立ち寄れるスポットです。
三室戸寺 6月下旬~8月上旬
2006年の「そうだ京都、行こう。」で取り上げられたお寺です。
250鉢、約100種類の蓮が揃っています。
鉢ですととても近くまで寄れますので、写真が綺麗に取れるのが嬉しいです。
法金剛院 7/10~8/1
受付7:30~12:30 閉門13:00
京都では蓮の名所として有名です。
蓮は朝に花が開きますので、早朝拝観がおすすめです。
色とりどりの蓮の花を楽しんで下さい。
勧修寺 7月下旬~8月下旬
8月上旬頃に最盛期を迎える、遅咲きの蓮が多いので他で見逃してしまった場合でも安心です。
イベント
貴船川床 ~9/30
京都の夏の風物詩、川床。
京都市北部の貴船は、町中より気温が10℃くらい低いので夏はとても涼しく、天然のクーラーの中にいる様です。
お座敷のすぐ下を川が流れるというシチュエーションはなかなか味わえません。
一度は訪れてみて下さい!
川床へ行った後は、貴船神社で参拝。
「水占い」も有名ですが、神社オリジナルの御神水を使ったコスメもおすすめです。
鴨川納涼床 ~10/31(例年は9/30まで)

こちらは京都市中心部、鴨川沿いのお店で味わえる床です。
夜風に当たりながら、ゆっくり寛げます。
お座敷だけでなく、椅子席のお店もありますので、お好みのお店選びをして下さい。
東福寺・青紅葉ライトアップ ~8/9 ※有料(要予約)
18:00~21:00 最終受付20:00
東福寺史上初!国宝&青紅葉のライトアップが開催されています。
紅葉が綺麗なのですから、青紅葉も綺麗に決まってますよね!
「通天橋」「東西両渓谷の青紅葉」「国宝の三門」「本堂」「愛染堂」「東福寺本坊庭園」が初めてライトアップされます!
広大な境内に見所が点在してるので、密を避けながら拝観できます。
幻想的な光に浮かぶ青紅葉の庭園を散策できるなんて素敵ですね。
東福寺 天得院ライトアップ ~7/18
受付18:00~20:00
桔梗の花が咲き揃う、初夏の特別公開です。
桃山時代に作られたという枯山水庭園は、美しい杉苔で一面が覆われています。
約300本の桔梗が出迎えてくれます。
夜はお抹茶が頂けますので、雅な気分をお楽しみくださいませ。
泉屋博古館 特別展「ゆかた 浴衣 YUKATA」 ~7/19まで
江戸時代の浴衣から、日本画家・鏑木清方等の近代画家がデザインした浴衣や、人間国宝の浴衣など様々な作品が展示されています。
「粋」な図案を見るのが楽しみです。
浴衣や着物で来館すると、入場料が2割引きになるそうです!
細見美術館 「集う人々-描かれた江戸のおしゃれ-」 ~8/15
江戸や京都等都市の様子を描いた「名所図屏風」や「遊楽図」、葛飾北斎の肉筆画「五美人図」、「江戸風俗図巻」等、時代の先端をいく人々の美意識やファッションに触れることが出来ます。
当時の着物の着方や色合わせは、興味を惹かれます。
あわせて調度品も展示されるとの事ですので、勉強にも目の保養にも良いですね。
行事
祇園祭
日本三大祭りの一つ、祇園祭。京都の年中行事の中でも盛り上がりNO.1です!
7/1~7/31の一か月間行われます。
例年ですと、神輿渡御、山鉾巡行が山場になるのですが、昨年に引き続きこちらは中止に。
とても残念です。
規模を縮小して、その他の神事は執り行われる様です。
「宵山」(山鉾巡行日の前夜、7/16の夜と7/23の夜)には、今年は18基限定で鉾が建ち、夜19時まで行う予定です。(屋台は出ないので注意)
祇園祭の由来
今から約1100年前、平安時代に京都で流行した疫病を鎮めるため「祇園社」(今の八坂神社)で66本の鉾(当時の国の数)を作り、疫病退散を祈願したのが始まりです。
現在の山鉾巡行は33基あり、各々にご神体が祀られています。
鉾は1本の釘も使わず、縄だけで組み立てます。
それぞれの山鉾町の方々は、お囃子や鉾の建て方など伝統を絶やさない様に尽力し、後継の方に伝えております。
また、祇園祭に携わる方々は期間中きゅうりを食べないそうです。理由はきゅうりの断面が八坂神社の御神紋、木瓜紋に似ている為です。
山
松や杉の木に飾りがついています。
高さは地上約15m、重さは約500㎏~8t、飾りや人形にそれぞれの特徴が出てます。
補助車輪を付け、昇方と呼ばれる20名程で巡行します。
鉾
真木という中心の柱があります。
高さは約25m、重さは約10~12t。
巡行では曳方の他に、屋根方、音頭取り、車方、はやし方と呼ばれる人たちが携わっています。
鉾の組み立てから、巡行及び解体には約180人もの人手が必要です。
茅の輪潜り (八坂神社)
夏越の祓
一年の半分に当たる6/30に、半年間の罪や穢れを祓い、これからの半年間を健康に過ごせるように祈願する神事の事です。
大体の神社は6/30に執り行われますが、八坂神社では6/30の「大祓式」と、7/31の「疫病社夏越祭」があります。
7月の一か月間は疫病社の鳥居に茅の輪が設置されますので、密にならないようにしましょう。
茅の輪のくぐり方
- 1周目 正面でお辞儀をし、左足で茅の輪を跨ぎ、左回りで正面に戻ります。
- 2週目 正面でお辞儀をし、右足で茅の輪を跨ぎ、右回りで正面に戻ります。
- 3週目 一週目と同じく、正面でお辞儀をし、左足で茅の輪を跨ぎ、左回りで正面に戻ります。
- 正面でお辞儀をし、左足で茅の輪を跨ぎ、参拝する。
茅の輪近くに「参拝の仕方」が書いてありますので、覚えていなくても大丈夫です。
熱中症などにお気を付けて、お体ご自愛くださいませ。
いかがでしたでしょうか?
次回は、主だった祇園祭の山鉾をご紹介していきます!