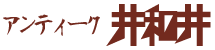9月は「月」に関する行事が沢山あります。
京都でも多くの催しがありますので、いくつかご紹介していきます!
行事
京都では、各所で名月をめでる観月祭が行われます。
平安時代には、貴族の間で観月の宴や舟遊びが盛んに催されていたそうです。
その当時に思いを馳せて、ロマンを感じてみましょう。
中秋の名月とは
旧暦では7,8,9月を秋としており、その真ん中の8月15日を「中秋」と言い、その晩に上がる月の事を中秋の月と呼びました。
また新月が毎月の1日にあたりましたので、15日は満月もしくは満月に近い月が見られました。
初秋は徐々に空気も冷たくなり、秋晴れも続きます。
空も高く、また月も綺麗に見えるので中秋の名月と呼ばれるようになったそうです。
※旧暦と新暦には1~2か月のずれがある為、現在は年によって9月もしくは10月になります。
※コロナウイルス感染拡大防止による中止や、天候により内容が変更になる場合がございます。
お出かけの際には各公式サイトなどで確認をお願い致します。
神泉苑 ~観月会~ 9/20
18:00~20:30
平安時代、天皇や公家達が大池に舟を浮かべて歌や花、音楽を楽しみました。
特別ご朱印帳の授与あり
18:00~ 本堂にて観月法要
18:30~ 庭園特別拝観
19:00~ 龍王社拝殿にて奉納演奏
※お茶席は中止となっております。
八坂神社 ~祇園社観月祭~ 9/21
※今年は奉納行事を取り止め本殿にて神事のみ執り行います。
毎年中秋の名月の夜に、舞殿にて舞楽、管弦、筝曲、太鼓などの伝統芸能が奉納されます。(拝観自由)
18:15~ 京都女子大学交響楽団による交響曲演奏
19:00~ 祭典と和歌の披講
19:30~ 管弦、舞楽、筝曲、太鼓の奉納
上賀茂神社 ~加茂観月祭~ 9/21
17:00~20:00
芝生内「馬場殿」で神事を行い、終了後には音楽、仕舞の奉納行事が行われます。
行事の後に、先着300名に「月見団子」の整理券が配布され、最後ににごり酒の振る舞いも予定されています。
下鴨神社 ~名月管弦祭~ 9/21
17:30~21:00
雅楽や神楽等の神事の後、管弦の調べを聞きながら名月を鑑賞します。
月見のお茶席¥1000
平野神社 ~名月祭~
※今年は奉納行事・接待行事は中止
18:30~21:30
神前に月見団子、薄、里芋が供えられ、琴や尺八の演奏、日舞、舞楽の奉納が行われます。
境内に設えた抹茶席は¥500で楽しめます。
長岡天満宮 ~名月祭~ 9/21
18:30~21:00
本殿での神事後、神楽殿で神楽・琵琶等の伝統芸能が奉納されます。
社務所前広庭ではお茶席が設けられ、八条ヶ池の錦水亭でお弁当を頂く事も出来ます。
イベント
大山崎山荘美術館 「和光絶佳展 ~令和時代の超工芸~」 9/18~12/5

日本の美意識に根差した工芸的な作品で、今最も注目されている1970年以降に生まれた作家12人を紹介しています。
・舘鼻典孝…遊女が履く高下駄から着想を得た代表作「ヒールレスシューズ」が有名。
・桑田卓郎…陶芸の枠を超える表現を発表し続けています。
・池田晃将…漆、螺鈿の伝統工芸による緻密な作品を制作する、漆芸美術作家。
・深堀隆介…金魚絵師。
・山本茜…截金ガラス作家。
・見附正康…陶芸家。九谷焼の伝統的な赤絵緻密画を代表する作家。
・新里明士…陶芸家。器自体が光る様な「光器」という作品で注目を集めています。
・高橋賢悟…「死生観」と「再生」をテーマにした鋳造作家(主にアルミ)。
・安達大吾…板締め絞りを中心に滲みを生かしたオリジナルテキスタイルを制作しています。
・坂井直樹…コンセプター。オリンパスの「O・Product」をはじめ、数々のヒット商品を生み出す。
・佐合道子…陶芸家。陶による「いきものらしさ」の探求。
・橋本千毅…漆工芸家。蒔絵、螺鈿を中心に作品を制作されています。
清水三年坂美術館 「絢爛たる刀装具 石黒派」 8/7~10/24
刀装具は刀剣の保護、外装の為の部品です。
石黒派は石黒政常を祖とする在野(公職に就かず、民間で活動する事)の彫金家の一派です。
江戸後期から末期にかけて多くの門弟を有し、花鳥を描き出す精巧な高彫色絵の手法を得意としました。
江戸の職人たちの緻密な作品をお楽しみ下さい。
泉屋博古館 「木島櫻谷 四季の金屏風」

四季それぞれの花が咲く、四双の金屏風。
大正時代、大阪茶臼山に新築された住友家本邸の為に製作されました。
春夏秋冬の黄金に輝く屏風をご堪能下さい。
野村美術館 「深まりゆく秋 ~初秋、晩秋の取り合わせ~」 9/11~12/5(前期・後期で展示替えあり)
茶の湯の「秋」をテーマにした展示はありそうでなかった様に思われます。
前期(9/11~10/24)…残暑の中、涼を呼ぶ風に乗って届く虫の声、長寿を願って菊の花を包む着せ綿の故事(菊慈童)等に思いを馳せる、初秋の取り合わせ。
後期(10/26~12/5)…長夜に眺める月の満ち欠け、山を錦に染める紅葉等を思い描く晩秋の取り合わせ。
前期・後期で違った楽しみ方が出来るとあって、2度行くのが楽しみです。
お茶をする方も、しない方も存分に楽しめそうですね。
※「泉屋博古館」と「野村美術館」は相互割引があります!
《対象の展覧会》
泉屋博古館
・木島櫻谷 四季の金屏風 9/11~10/24
・伝世の茶道具 ~珠玉の住友コレクション~ 11/6~12/12
野村美術館
・深まりゆく秋 ~初秋・晩秋の取り合わせ~ 9/11~12/5
《泉屋博古館に入館された方》
野村美術館へ入館時¥100引き(他の割引きと併用不可)。
《野村美術館に入館された方》
花たより
初秋を楽しむ可憐な花々をご紹介します。
萩

秋の七草(萩・薄・桔梗・撫子・葛・藤袴・女郎花)の一つとして有名ですね。
丸い葉に豆科らしいお花が可愛いです。
秋のお彼岸に備える「おはぎ」は、秋を代表する「萩」に因んで「御萩」と呼ばれるようになったそうです。
秋明菊

名前に「菊」が付きますが菊の仲間ではなく、キンポウゲ科のアネモネの仲間です。
別名は「貴船菊」。他にも「秋牡丹」、「しめ菊」、「紫衣菊」、「加賀菊」、「越前菊」、「唐菊」、「高麗菊」、「秋芍薬」等沢山の別名があります。
細くて長い茎に咲く花は、なんとも可憐です。
薄

秋の七草の一つです。
「尾花」とも呼ばれています。
赤紫色の花穂を咲かせ、花が咲いた後白い毛の生えた種子を付けます。
花と種子は万葉集の時代から、沢山の歌や詩に詠まれています。
秋はまだ始まったばかり。
芸術の秋、食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋…
それぞれの秋をお楽しみ下さい。