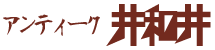着物と帯については以前紹介した記事で、何となく分かって頂けたかと思います。
今回は「はおりもの」についてのご紹介です。
一般には「もみじが色付き始めた頃から桜が咲くまで」と言われていますが、自分の体調や気候に合わせて着て頂いて差支えないと思います。
主に防寒や塵除け、おしゃれとして羽織るものですが、これにもマナーがあります!
どんな時に着るのか、またどういったシーンでは適さないのか。
詳しく見ていきましょう!
羽織
肌寒い季節に着物の上からはおります。洋服で言うとカーディガンの様なものです。
羽織の長さに決まりはありませんので、好みの長さで着て頂くのがいいでしょう。
レストランや室内でも着たままで大丈夫です。
夏用の塵・ほこり・紫外線除けとして、レースの物(夏羽織)もあります。
乳に、羽織紐や羽織チェーンを付けて前を留めて着用します。




羽織にも種類があるので、季節やシーンに分けて使い分けて下さい。
紋付黒羽織

黒地の羽織に1つまたは3つ紋が付いたもので、小紋や御召などの上に着ると略礼装になります。
学校の卒入式などによく用いられました。
1つ紋の方が使える幅が多いです。
絵羽織

友禅や絞り染め、刺繍などで肩から裾にかけて前面に柄が入ったものです。
お正月や観劇によく着用されました。
格が高い絵柄だと慶事の略礼装に使われることもありますが、殆どは外出着として着て頂けます。
袷羽織
袷、なので裏地が付いたものを指します。
着る時期は袷の着物と一緒です。
単衣羽織
単衣着物と同じく、裏地を付けません。
着る時期も単衣の着物の時期と同じですが、ウールの場合は冬に着用します。
※袷・単衣に関してはこちらの記事をご覧ください。
夏羽織

絽や紗、レースなどで仕立てた夏の羽織です。
6月~9月まで着用出来ます。
略礼装や、お洒落着として用います。
茶羽織
一般的な羽織と違い、家での防寒着として着用します。
丈やたもとは通常より短く、両サイドの襠もありません。
羽織紐は使わず、衿に着けた共布紐を結びます。
最近では旅館の浴衣に着る場合が多いようです。
羽織にも色々種類がありますが、一般的には普段着なので礼装には向きません。
どうしても略礼装で着たい場合には、紋を入れ、色柄にも注意してください。
コート
コートにも種類や格があります。
礼装に使える物や普段使いに適している物があるので、シーンによって使い分けて下さい。
道行コート

道行とも呼ばれます。
外出用のコートで、衿の形が額縁の様に角ばっているのが特徴です。
前を合わせてホックなどで留めます。
礼装用なので、留袖や訪問着などを着る時に用いますが、紬で作られたものはカジュアルなものに使えます。
また、無地の道行コートは最も格が高いコートになります。
丈は五分丈や七分丈が一般的です。
こちらはコートなので、室内に入る時には脱ぐのがマナーです。
道中着
前を合わせて紐で結ぶので、身幅の調整がしやすいです。
着物と衿合わせが同じになっています。
道行コートの衿とは違い、裾に向かって衿幅が広くなっています。
こちらは略式コートになるので、正装には使えません。
1番普段使いの出来るコートです。
コートなので、室内では脱ぎましょう。
雨ゴート
名前の通り、雨の日に着ます。
濡れないよう、着物の裾を隠す長さ(着物より1~2㎝長いもの)が適しています。
撥水加工をしたり、木綿や化繊で仕立てる場合が殆どです。
こちらは季節を問わず単衣で仕立てます。夏だと撥水加工をした紗をよく見かけます。
対丈で着る「1部式」と、上下で分かれている「2部式」があります。
礼装に用いる時は1部式の方が無難です。その場合生地や柄もカジュアルになり過ぎないようにしましょう。
コートの衿の形
コートには様々な衿の形がありますが、その中でよく見かける6つの形をご紹介します。
道行衿
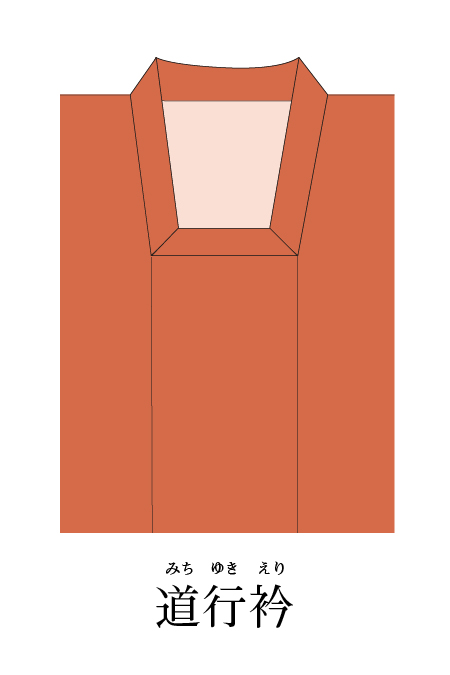
道行衿は、額縁のように四角くなっている衿になります。
一番スタンダードな衿の形で、フォーマルによく用いられます。
都衿
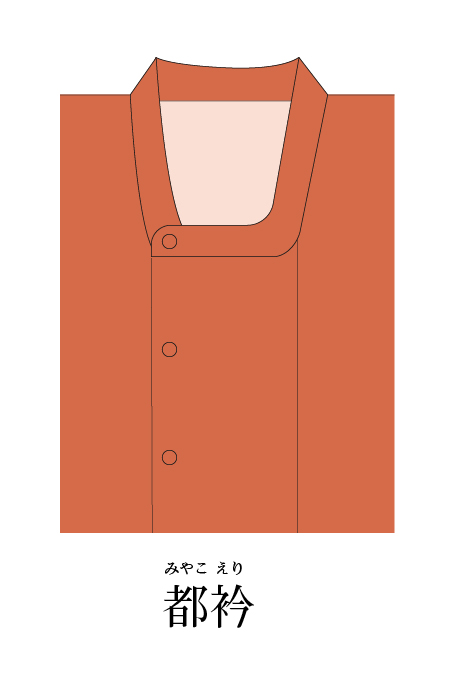
都衿は道行衿に似ていますが、角が丸みを帯びていて少し柔らかい印象を受けます。
こちらもフォーマルで使えますが、素材や色柄ではカジュアル使い出来ます。
千代田衿
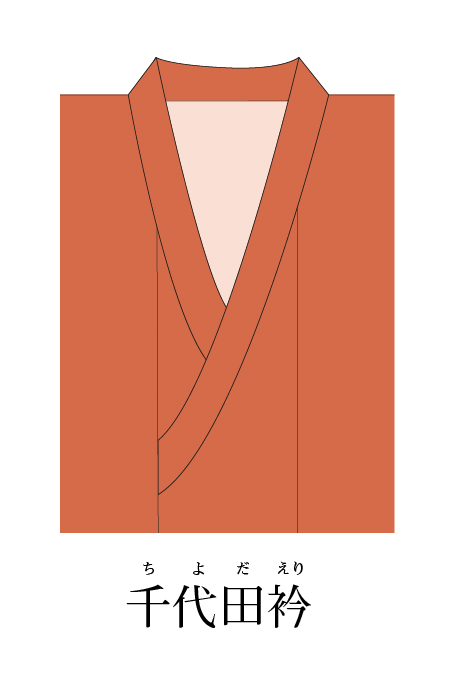
千代田衿は大正時代中期に、着物の衿とミックスして作られました。
道行衿などに比べると、胸元が開いているのでスッキリ見えます。
殆どはカジュアルな場面で着用され、素材や色柄によっては準フォーマルでも着用出来ます。
被布衿
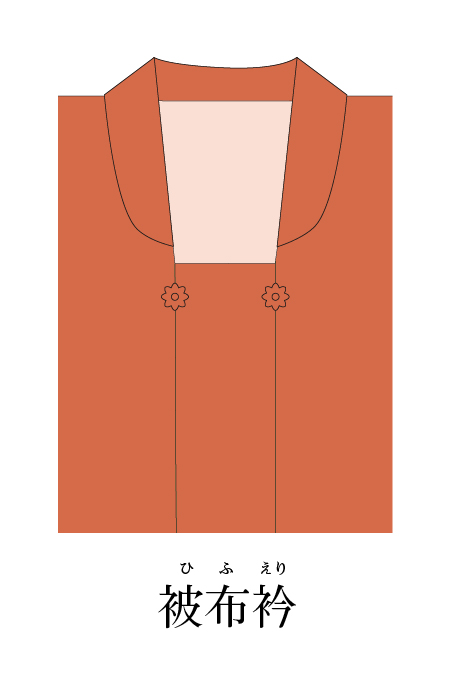
七五三で三歳の女の子が着ていることが多いですね。
他の衿と違い、被布衿は飾り紐がついています。
江戸時代中期にお座敷用の防寒具だった「被布」に使われていたのが被布衿です。
女性用というイメージがありますが、男女問わず着用出来ます。
色柄により、カジュアルから準フォーマルまでお使い頂けます。
道中衿
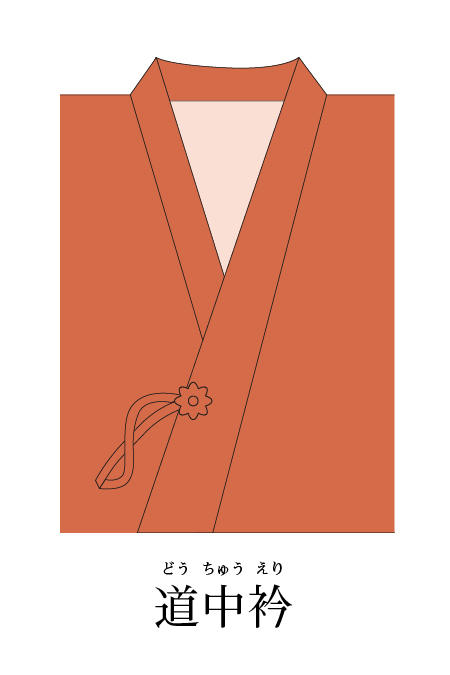
着物と同じ衿合わせで、飾り紐が付いています。
普段使いには丁度良いです。
きもの衿
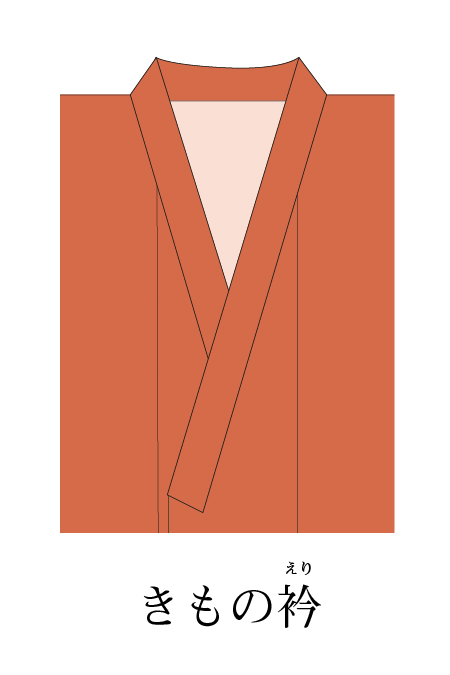
コートの衿の中で、最もカジュアルなきもの衿。
外側に付けた紐を腰で結ぶので、可愛らしく見えますね。
素材もカジュアル使い出来そうな物を選んだ方がいいでしょう。
普段何気なく使っている羽織やコートにも、シーンに合わせた装いや格があります。
知っていればいざという時困りませんので、是非チェックしてみて下さい!