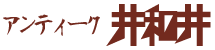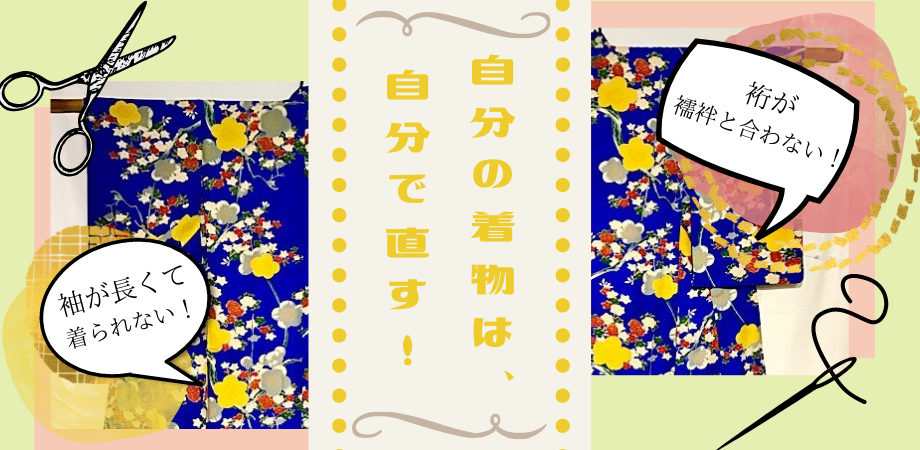
アンティーク着物を着るにあたり、必ず出くわすのがサイズの問題です。
現代の着物とは違い、袖丈などまちまちです。
自分で簡単に出来る襦袢と着物の袖丈・裄丈の合わせ方をご紹介します!
ℚ.着物より襦袢の方が、袖丈が長い場合はどうしたらいい?
A. 襦袢の袖を着物の袖丈に合わせて縫い上げます。
2通りのやり方がありますので、お好きな方を選んでやってみて下さい。
①裾を折り返す
襦袢の袖を裏返しにし、着物の袖丈より少し短めの位置を、内袖と外袖を一緒にして運針します。

内袖側へ折り上げ、落ちてこない様に縫って留めます。


※袖の内側がもこもこして嫌な方は、表側から縫っても大丈夫です。但し、襦袢など中に着る物に限ります。


②内袖と外袖を別々に縫う
襦袢の袖を裏返し、袖の真ん中辺りを内袖・外袖別々につまんで縫います。
仕上がりが着物の袖丈より気持ち短くなるようにします。
こちらの方法ですと、袂がスッキリするので、袖下がもたつくのが嫌な方にオススメです。
こちらも表側から縫っても問題ありませんが、中に着る物に限ります。


ℚ. 着物より襦袢の方が、袖丈が短い場合は?
A. 先程と同様に、今度は着物の袖を折り返して縫います。
着物は襦袢の袖よりも、ほんの少し長くなるようにしましょう。
ℚ. 着物より襦袢の方が、裄が長い!
A. 襦袢の肩山と袖山をつまんで縫います。
初めに、着物のサイズを二か所測ります。
・背中心から袖付まで
・袖付から袖口まで
次に襦袢も同じように測り、着物と同じ長さになる様、子供の肩揚げ同様につまんで縫います。


両方縫うのが嫌な方は、袖だけで調節しても〇
他にも、襦袢の袖山を着物から出ない長さになる様つまんで、安全ピンで留める方法もあります。


※こちらはピンが刺さってしまう可能性がありますのであまりオススメ出来ませんが、急いでいる時など応急処置として使えます。
ℚ. 「筒袖半襦袢」とは?
A. 七分丈程の長さの、筒状の袖が付いた半襦袢です。
初めから振りの無い襦袢を選んでおくと、袖丈を気にする必要はありません。
普段着であれば襦袢の袖が見えなくてもいいかと思います。
着物のサイズを気にせず着られますが、短所としては着物の袖口の皮脂汚れを防ぐことが出来ません。
そんな時は袖口に、ガロンレースやリボンを縫っておくと良いです。
汚れたら取り換えられるので、着物を守ることが出来ます。
※ガロンレース…汚れやダメージ防止に使う、リボン状の布。主に裾や袖口に使います。

色々な創意工夫をして、アンティーク着物を楽しみましょう!